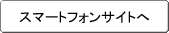雇用主は、社員の勤務外における私的行為を理由として懲戒や解雇を行うことができるのか? |
最近のニュースで、勤務時間外に社員が私的に行った行為が問題となった二つの事例が報道されました。
一つ目は、ある有名自動車メーカーの販売員が勤務時間外に自家用のスポーツカーを運転し、公道で逆走・追い越し違反をしたというもの。
もう一つは、ある牛肉鍋店の従業員が、閉店後に同僚と一緒に粥店で食事をしていたところ、隣の客が自分と意見の違う話題を大声で話していたため、口論から殴り合いに発展したというものです。
これら二つの事件はインターネット上で大きな話題となり、
一件目の自動車会社は「社内規定に基づき当該営業員を停職処分にした」と発表し、
二件目の牛肉鍋店は、ネット上で「星1つ評価」が殺到した後、「問題の従業員を即時解雇した」と説明しました。
しかし、どちらの事件も勤務時間外、かつ職務遂行中ではなく、完全に私生活上の行為です。
では、雇用主はこのような「社員の私的行為」を理由に懲戒処分や解雇を行うことができるのでしょうか?
■ 原則:私生活上の行為は雇用主の懲戒権の範囲外
社員の勤務中の行為については、雇用主の指揮監督の下にあり、一定の懲戒権が認められます。
しかし、勤務時間外で職務に無関係な行為は、一般的に社員の私生活の範囲に属し、雇用主が自由に介入できる領域ではありません。
したがって、原則として社員の私生活上の行為は、雇用主の支配・管理の範囲外であり、これを理由に懲戒や解雇することはできません。
もっとも、台湾の司法実務では、一定の条件を満たす場合に限り、例外的に私的行為を懲戒対象に含めることを認めた判例があります。
たとえば、最高法院(最高裁)1982年度台上字第1786号判決は次のように述べています:
「労使関係は労働力を中心とした時間・空間上の結合関係であり、労働者と雇用主の人格的結合関係ではない。
よって、勤務時間外の業務に無関係な行為は労働者の私生活に属し、雇用主が任意に支配できるものではない。
ただし、労働者の行為が事業活動と直接関連し、かつ事業の社会的評価を損なう場合で、
事業秩序維持のために必要なときに限り、懲戒の対象とすることができる。」
つまり、労働者の行為が事業活動と直接関係し、会社の社会的評価を損なう場合に限って、例外的に私的行為を懲戒の対象とすることが許されるということです。
■ 例外を認めるための条件
雇用主が懲戒権を明確に行使するためには、就業規則や労働契約書において懲戒事項と範囲を具体的に定めておく必要があります。
すなわち、「社員が私生活でどのような行為を行ってはならないか」、
「それが会社にどのような具体的損害を与えた場合に懲戒対象となるか」を明記しておくことが求められます。
たとえば、社員の個人的な借金問題が原因で債権者が会社に押しかけ、業務を妨害したり、会社の設備を破損させた場合には、会社秩序への悪影響が明確であるため、懲戒の対象と認められる可能性があります。
ただし、仮に懲戒権が認められる場合でも、**比例原則(処分の重さは行為の重大さに見合うべきという原則)**を守らなければなりません。
行為の内容や影響の程度に応じて、口頭注意・戒告・減給・停職など処分の軽重を区別すべきであり、過度に重い処分を行えば「懲戒権の濫用」と判断され、無効になる可能性があります。
■ 解雇は「最後の手段」
解雇は最も重い懲戒処分であり、台湾の実務では「最後手段性の原則」が確立しています。
すなわち、「情状重大」とは、その事由により労働関係の継続が困難になり、雇用主に即時の契約解除権を認める必要がある場合を指します。
解雇が合法と認められるためには、
社員の違反行為が労働契約や就業規則の具体的な条項に違反し、かつ解雇以外の懲戒では関係継続が期待できない程度に重大である必要があります。
また、判断にあたっては、事業の性質、違反行為の態様、会社への損害の程度、勤務年数などを総合的に考慮します。
■ 結論
したがって、社員が勤務外に行った私的行為について、雇用主は原則として懲戒処分を行ったり、契約を一方的に解除したりすることはできません。
ただし、
労働契約や就業規則において明確に禁止事項と懲戒の基準が定められており、
その私的行為が会社に実質的かつ具体的な悪影響を与えた場合に限り、
例外的に懲戒が認められます。
さらに、解雇という最も厳しい処分を行う場合には、労働基準法第11条・第12条に定められた法定事由に該当し、かつ最後手段性の原則を満たすことが必要です。
雇用主が感情的判断や社会的非難への対応目的で、勤務時間外の私的行為を理由に懲戒・解雇を行うことは、労働者の権利保護の観点から明確に違法とされます。
(筆者)林俊宏弁護士