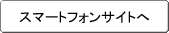労働権益の重要性と実践知識を若者へ伝える 台湾労働局啓蒙活動 |
台湾では今後労働者の権益を守るために学校へ労働教育を導入!
以下は台北市労働局から送られてきた文章になります。
学校へ、労働権益と尊厳・平等の種をまく —
「労働好YOUNG 校園前進」労働権益啓発講座の経験
台北市産業総工会 秘書長 陳淑綸
108課綱(新カリキュラム)で素養重視と生活への応用が教育の潮流となる中、労働教育の重要性が徐々に注目されるようになってきた。台北市労働局では特別に「労働好YOUNG 校園前進—国・高校生必修の労働権利授業」を用意し、市内の各国・高等学校が無料で申請できるようにしている。テーマは「労働時事」—労働三権や職場の平等といった概念を重視するもの、また「アルバイトで知っておくべき労働権益」—職場における基本的な法律の保障に重点を置いたものがある。授業や集会の時間を活用し、労働局が弁護士、学者、実務家などを招いて講義を行う。私は労働組合の経験から講師として招かれたが、これは単なる法律知識の伝達ではなく、市民意識を芽生えさせるきっかけになると強く感じた。
国中(中学校)や普通高校での講義では、労働権益と国連人権条約、憲法の基本権との関係や実務での応用を特に強調する。例えば「会社が女性制服をスカートのみと規定するのは合理的か?」というテーマを取り上げ、桃園市の客室乗務員職業組合が、国内航空会社の「女性客室乗務員はスカート着用のみ」という規定に対して申立てを行い、記者会見を繰り返して社会的注目を集めた事例を紹介する。最終的に国家人権委員会が、CEDAW(女子差別撤廃条約)を引用してこの規定が性別平等の原則に反すると認定し、航空会社がパンツスタイルを選べるようになった。この事例は、基本的人権、憲法上の労働権、団結権との関連を同時に示しており、また職場で当たり前とされていることでも、実は性別の固定観念による差別や不平等が潜んでいる可能性があることを生徒に理解させ、労働権の意識を持って挑戦することで社会を変えていけることを伝える。
一方、技術系・職業高校などの講義では、生徒の多くがすでにアルバイトや実習経験を持っているため、より実務的な注意点を強調する。例えば「労働契約」。多くの生徒は契約書を交わしたことがない、または契約内容が理解できない(例:1分遅刻で50元罰金、退職時に違約金を支払う等)という。中には白紙書類や手形に署名したケースもあり、契約リテラシー向上が急務であることがわかる。また、雇用主は法律に基づき、労働保険、健康保険、雇用保険、労働退職金積立、職業災害保険に加入させる義務がある。アルバイトだからといって未加入や高給低報(実際の給与より低い額で申告)にすることは認められない。生徒からは、事業所の倒産による未払い賃金、試用期間終了後に保険加入と告げられた、休憩時間がない、掃除や研修時間を労働時間に含めない、勤務中のケガを自己責任とされた、などの相談も寄せられる。こうした事例から、雇用主の法令遵守意識が低い場合には、労働者自身が法律を理解して権利を守る必要があることがわかる。
「魚を与えるより、魚の釣り方を教えるべき」。校内での講義では、求職詐欺防止やアルバイトで注意すべき「七不三要(7つの禁止と3つの必須事項)」という合言葉を紹介するだけでなく、生徒に「情報を正しく見極め、問題を効果的に解決する」方法を教えることを重視している。そのため、会社情報や労働保険加入状況を確認できる政府窓口、台北市の「1999」や労働局「労働権益センター」の無料法律相談など、活用できる支援制度を案内している。大事なのは、こうした保護制度を知り、自ら助けを求める意欲を持つことだ。参加意欲を高めるため、労働局は小さな景品とクイズ形式のインタラクティブな質疑応答を用意し、生徒からは活発な発言が寄せられる。活動後には「アルバイトにも休暇取得の権利があると初めて知った」「以前、社長に『自分の不注意で転んだのだから労災ではない』と言われたが、間違いだった」「七不三要は本当に役立つから友達にシェアする」といった感想もあった。
労働教育は単なる教科内容ではなく、すべての若者が自信を持ち、合法かつ安全に職場に入っていくための重要な素養である。今日まいた種が、将来、自分や他者の権利を守る力へと成長することを願っている。