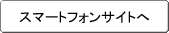台湾の障害者雇用の平等を実現するために |
社員が障害に直面したとき、「合理的配慮」をどう活用するか?
労働力発展署や障害者連盟と共同で「障害者就業サービスにおける合理的配慮指針」を編纂しました。アメリカ、カナダ、オーストラリア、韓国など数十年の経験を集約し、多くの事例を交えて「合理的配慮」とは何かを解説しています。その中には、雇用主にとっても非常に参考となる考え方が数多く含まれています。
1. 合理的配慮は新しい概念ではない
「合理的配慮(Reasonable Accommodation)」は国連《障害者権利条約(CRPD)》における重要な概念です。障害者の具体的なニーズに応じて、過度な負担(不当な負担)をかけない範囲で、施設・設備、職務内容(労働時間、分担、生産プロセスなど)、人的サポート、制度規範といった面で必要かつ適切な調整を行うものです。
台湾でもすでに強い法的拘束力を持ちつつあり、単なる理念ではなく、法規によって雇用主の義務として明確化されています。
2. 標準を下げるためではなく「実質的平等」のため
合理的配慮は障害者のために基準を下げるものではありません。理念は「スタート地点を調整し、ゴールは平等に」ということです。
例えば、技能試験で合格点を下げる必要はなく、試験の方式や環境を工夫することで障害者が公平に挑戦できるようにします。職場でも同様に、基準を緩めるのではなく環境や制度を調整することで「実質的な平等」を実現します。
3. 雇用主の負担も重視する
合理的配慮は労使双方に関わるものであり、労働者の要望の合理性と雇用主の負担可能性のバランスを重視します。企業の規模によって対応できる範囲が異なるのは当然であり、何が「合理的」か、どこまで「負担可能」かを判断するための具体的な基準や事例がガイドラインで示されています。
4. 企業は自社のニーズから出発すべき
ある企業はソフトウェアテスト部門の人材流動率が非常に高かったため、自閉症者の持つ集中力や検査能力に注目し、積極的に採用しました。その結果、流動率は10分の1に低下し、生産性は大幅に向上しました。
合理的配慮は単なる義務や福祉目的ではなく、企業自身の課題解決につながるものです。
5. 配慮は必ずしも「高コスト・大規模」とは限らない
障害者への配慮というと「環境改修に莫大な費用がかかる」と誤解されがちですが、実際は小さな調整で解決することも多く、政府の補助制度を活用できる場合もあります。
6. 完璧な準備がなくても始められる
合理的配慮は「個別化」が大前提です。同じ障害でも人によって必要な調整は異なります。重要なのは、実際に取り組む中で調整を積み重ねていく姿勢です。
台湾ではすでに参考資料や専門団体、支援ネットワークが整いつつあり、実践の中で必ず方法を見つけることができます。
要するに、「合理的配慮」とは障害者に一方的に便宜を図ることではなく、雇用主にとってもプラスとなる「実質的平等」のための調整であり、企業の成長や職場改善のヒントにもなるのです。